会社の「定款」 有効活用できていますか?
会社設立時に作成した定款の内容をきちんと把握していますか。定款は「会社の憲法」です。記載内容によっては、会社経営に悪影響を及ぼすリスクとなっている可能性もあります。今回は中小企業のための定款活用術をご紹介します。ぜひお手元に定款を置いてご覧ください。
(掲載日 2025/02/12)
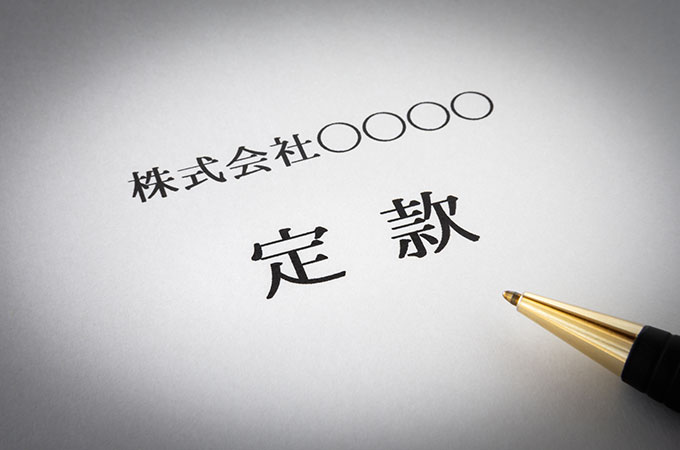
定款を経営に活かす!?中小企業のための「定款」活用術
「すみません、定款のコピーをいただけますか?」
ある日、メインバンクからそう求められ、慌てて探し始めた建設業の社長。設立時から20年、経営環境は大きく変化していたにもかかわらず、定款は金庫の奥底で眠ったままでした。
多くの中小企業経営者にとって、定款は会社設立時に作成が必要な法的書類の一つという認識に留まっているのではないでしょうか。実際、経営者の方々との対話を通じて、定款の内容を十分に理解し活用されている企業は決して多くないと感じています。しかし、定款は単なる法的要件を満たすための文書ではなく、企業経営における重要な戦略ツールとして活用できる可能性を秘めています。本稿では、定款の基本的な理解から始め、経営戦略への具体的な活用方法まで、実践的な視点でご紹介していきます。
定款とは
定款は、会社の「憲法」とも呼ばれ、就業規則や組織規程など様々な社内規程の中で最上位に位置づけられる基本規則です。商号、目的、本店所在地といった基本的事項から、株式や役員構成に関する規定まで、会社運営の根幹となるルールを定めています。定款は会社の基本方針を示すだけでなく、株主総会の運営や役員の選任など、具体的な意思決定の手続きも規定しており、会社運営の実務的な指針としても重要な役割を果たしています。定款の重要性
定款の重要性は、単なる形式的な規程文書という側面を超えています。第一に、定款には会社の存在意義や将来への展望、経営者の想いが込められているべきものです。第二に、株主や役員間での意見対立が生じた際の最終的な判断基準としても機能し、会社運営の安定性を確保する重要な役割を担っています。さらに、取引先との関係においても、設立時に公証役場での認証を受けた公的文書として、会社の信頼性を裏付ける重要な存在となっています。だからこそ、形だけの存在として眠らせることなく、会社の成長を支える基盤として、より積極的に経営に活かしていくことが望まれます。
企業理念・ミッション・ビジョンとの連携
企業経営において、理念やミッション、ビジョンは組織の方向性を示す羅針盤としての役割を果たします。これらは通常、社内の掲示物やウェブサイト、会社案内などで打ち出されていますが、それだけでは単なる「スローガン」に留まってしまう可能性があります。そこで注目したいのが、定款との連携です。定款に企業理念やミッション、ビジョンを反映させることで、それらを経営の重要な指針として位置づけ、組織全体での共通認識を高めます。多くの企業では、これらが別々に存在し、相互の関連性が意識されていないことが少なくありません。両者を適切に連携させることで、組織としての一貫性が強化され、より効果的な経営の推進が可能となります。
例えば、株式会社良品計画では、定款の第2条に『「人と自然とモノの望ましい関係と心豊かな人間社会」を考えた商品、サービス、店舗、活動を通じて「感じ良い暮らしと社会」の実現に貢献することを企業理念とする』と掲げ、会社の使命や果たすべき役割を詳細に記載しています。これは企業理念と定款を効果的に結びつけた好例といえます。
サイボウズ株式会社では、企業理念の実現を経営の第一義とし、その重要性から企業理念自体を株主総会で決議して決めることを定款で規定しています(第18条)。実際に2024年の定時株主総会では企業理念の一部変更が行われており、定款を通じて企業理念を経営の核心に据えています。
このように、定款を通じて企業理念やミッション、ビジョンを経営の中核に位置づける取り組みは、組織の一体感を高め、企業価値の向上につながる実践として注目されています。

リスク管理ツールとしての定款
定款は、企業におけるリスク管理の重要なツールとしても機能します。特に中小企業では、経営資源を効率的に活用していく必要があり、様々なリスクに対する備えが重要です。この点でも定款を効果的に活用することができます。1.株式譲渡制限
株式は、自由に他人に譲渡できるのが原則です。しかしながら、中小企業にとって、株式の分散や外部への流出は大きなリスクとなります。たとえば、先代社長の方針で親族内や社員にも幅広く株式を持たせてきた結果、後継者である現社長の代になり、社長の持株比率がわずか30%で特別決議の拒否権さえ確保できていない、という状況に陥るケースも想定されます。このような事態を未然に防ぐためにも、定款での株式譲渡制限規定により、このリスクを適切にコントロールすることが重要です。2.機関設計の柔軟化
会社の規模や状況に応じて、取締役会の設置有無や役員の員数など、定款で柔軟な機関設計のルールを定めることで、ガバナンス体制を最適化することができます。また、一人代表取締役制を採用する会社では、事故や急病など不測の事態に備えて、補欠の取締役を選任できる旨を定款に定めておくことで、経営の空白期間を防ぐことができます。3.役員の権限規定
中小企業においては、社長の迅速な意思決定が競争力の源泉となる一方で、重要な局面では組織的な判断も求められます。例えば、一定額以上の借入や重要な資産取得などは取締役会の承認に加えて第三者の意見を求める旨を定款に定めることで、経営の機動性と組織的なチェック機能を両立することができます。
事業承継を見据えた定款の活用
創業100年を超えるような老舗企業から新興のベンチャー企業まで、事業承継は企業の存続にとって避けられない重要な課題です。特に同族経営の企業では、経営権を巡る対立や相続による株式の分散によって長年築いてきた事業やブランド価値が失われるリスクが存在します。このような事態を防ぎ、円滑な事業承継を実現するためにも、定款は重要なツールとして機能します。1.種類株式等の活用
株式には、普通の株式とは異なる権利や制限を持つ「種類株式」があります。これを活用することで、経営権と経済的利益を分けるなど、事業承継を円滑に行うための工夫ができます。⑴議決権制限株式
通常の株式には会社の重要な決定に参加できる議決権がありますが、この株式は議決権が制限されています。例えば、後継者には普通株式を、その他の相続人には議決権制限株式を引き継がせることで、経営権の集中を図れます。
⑵拒否権付株式(黄金株)
この株式を持っている人は、特定の重要な決定に対して「待った」をかけることができます。例えば、定款の変更や会社の合併といった重要な決定には、この株式を持つ人の同意が必要となります。
⑶配当優先株式
会社の利益から配当を受け取る際に、他の株主より優先的に受け取れる権利が付いた株式です。経営には参加せず、安定的な配当収入を望む株主向けの株式といえます。
⑷属人的株式
特定の株主に特別な権利を与える株式です。非公開会会社の場合に限り、例えば「現社長が保有する株式のみ1株につき10の議決権を与える」といった設定ができます。これにより、少ない株数でも大きな影響力を持つことができます。
これらの種類株式等を活用することで、後継者への経営権の移行と現経営者の関与のバランスを取りながら、円滑な事業承継を実現することができます。ただし、導入にあたっては株主全員の同意が必要となる場合があるため、慎重に検討する必要があります。
2.相続人等に対する売渡請求
株主の相続が発生した場合、株式譲渡制限があっても相続人に株式が承継されてしまう可能性があります。特に1990年(平成2年)以前に設立された会社では、7人以上の発起人(株主)が必要だったため、親族や知人に名義を借りただけの株主が残っているケースも多く、相続発生時に予期せぬ株式の分散が起こりやすい状況にあります。そこで、定款に「売渡請求条項」を設けることで、会社が相続人等に対して株式の売渡しを請求できるようになります。ただし、売渡請求権の行使には株主総会の特別決議*1が必要であり、また株式購入資金の確保にも留意が必要です。*1…株主総会の特別決議:通常の決議(普通決議)よりも高い議決要件が必要となる決議のことです。特別決議は、定款の変更や合併など、会社の根幹に関わる重要事項を決定する際に用いられます。原則、議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ、出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成をもって可決されます。
3.後継者育成のための定款活用
「後継者をいかに育てるか」は、事業承継における最大の課題の一つです。計画の実効性を高めるには、その中核部分を会社の基本規程である定款に反映させることも有効です。具体的には、代表権付与など権限委譲の段階を定款に明記し、後継者候補の計画的な育成を制度化します。また、相談役や顧問の職務・権限を適切に規定することで、前経営者から後継者への円滑な権限移行も図ります。このように、承継計画の要点を定款に組み込むことで、実効性の高い後継者育成が可能となります。
おわりに
定款は、単なる法的文書ではありません。それは、企業の過去、現在、未来をつなぐ重要な経営ツールとなり得るものです。特に中小企業において、定款を戦略的に活用することは、持続的な成長と企業価値の向上につながります。本稿で紹介した視点や方法論を参考に、ぜひ一度、自社の定款を見直してみてはいかがでしょうか。そこから、新たな経営の可能性が見えてくるかもしれません。
著者プロフィール

 はじめての方
はじめての方 無料経営分析
無料経営分析 お問合せ
お問合せ ログイン
ログイン


























