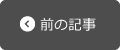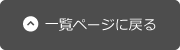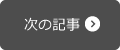営業や生産など部門間が対立することなく、同じ目標に向かって協力できている
営業や生産など部門間が対立することなく、同じ目標に向かって協力できている
営業部門には営業なりに生産部門や開発部門に対して主張したいことがあります。もっと売りやすいものを、売れるものを作って欲しいと。営業は顧客からのクレームの前面に立つ立場にあり、それに応えなければ営業活動もできません。
一方、生産部門では品質向上と納期の短縮化、在庫の圧縮、コストダウンが至上命令で、それには計画的に生産活動を進めるのが原則です。しかし、営業からお得意様からの要請であると、特急の割り込みをすると生産計画を乱して、あちらこちらに無理を生じさせ、結果的にコストアップになって

セクショナリズム(部門間対立)が生じる理由
営業部門には営業なりに、生産部門や開発部門に対して主張したいことがあります。もっと売りやすい物を、売れる物を作ってほしいと。営業は顧客からのクレームの前面に立つ立場にあり、それに応えなければ営業活動もできません。
一方、生産部門では品質向上と納期の短縮化、在庫の圧縮、コストダウンが至上命令で、それには計画的に生産活動を進めるのが原則です。しかし、営業からお得意様からの要請であると、特急の割り込みをすると生産計画を乱して、あちらこちらに無理を生じさせ、結果的にコストアップになってしまいます。また、シェア獲得優先による受注競争で採算割れに近い無理な受注をしてくると、それは結果的に生産部門にしわ寄せされることが多いものです。受注生産品が多いような工場の製造部門と設計部門との間でも不具合箇所が生ずると、責任のなすり合いでけんか腰になってしまうケースをよく見受けます。
部分最適から全体最適へ
それぞれの部門は一生懸命になって部分最適にはなっているかもしれま
せんが、全体最適になっているとは限りません。
第1に相互に連携しやすいように、情報の共有化を図ることが大事です。同じ情報をもとに議論すれば、結論への到達は早くなります。ワイガヤで議論すると隠れていたインフォーマル(非公式)情報も表にできます。これがさらに情報の共有を進め、コミュニケーションギャップを埋めるのです。オープンな議論ができる雰囲気にあるかどうかが重要です。混乱は不正確な情報に基づいて起こるものです。オープンな議論をすることと責任追及は別のことです。責任追及になれば、隠してしまって、真実の情報は誰もいい出しません。
第2には全体最適をめざすのですから、経営トップから、しっかりした大きな方針が打ち出されていることが大事です。大きな方針に基づいて、各組織が動いているということが理解できていれば、ベクトル合わせは可能になります。
第3に部門間をつなぐ人材を意識的に育てておくことです。ローテーションをするまでもなく、日常業務のなかで連携する場面をたくさんつくっておくわけです。壁を崩すのには職場横断的な委員会活動やプロジェクトチーム活動などを頻繁に開催するのが有効なのですが、原籍での日常業務とこれらチームでの活動が同時期に起こりますので、本人の負荷は大変なものになります。原籍での上司とプロジェクトチームのリーダーとが正当に評価をしないと、活動は活発になりません。職場代表が集まって、このような場が利害調整の場になってしまったのでは本末転倒です。前者の目標を見失わないように、目的意識とチェック、アクションのループを常に意識するような活動であってほしいです。
第4に職人的な人が中心になっている機械加工の職場などで見られるのですが、自分の担当する機械はきれいに整理整頓を徹底しているが、担当の機械以外についてはまったく関心を持たない。依頼されたことは完璧にこなすが、職場全体で協力して何かをしようとしても、非協力的になってしまうことがあります。年齢が高いケースが多いのですが、横につなぐことや、新人の育成を担当させる、職能の拡大を意識的に行う、などの必要があります。このような人は保守的で今までのやり方を変えたがりません。籠もっていては企業全体の生産性は上がらないということを納得してもらう必要があります。社長自らが話し合いの場に立ち会って、引き込むことが重要です。
Case Study
こうやって生かすプロジェクトチーム
X社の新製品開発のプロジェクトチームには、テーマ担当者(責任者)がいる。テーマ担当者は年功で選ばずに、その開発テーマに最も興味を持っている人を選ぶ。そのほうがチームにおけるリーダーシップが期待できるからだ。そうして選んだ責任者はチームの会議を見ていても全然違うという。チーム担当者は年齢に関係がないので、チーム員と職位が逆転することもある。
(各種計測機器製造・94人)
Y社は開発体制を一新、プロジェクトチーム制を導入した。核となる製品の開発スピードをアップさせるためだ。ヒット商品となったデジタル屈折計は、この新体制のもとで生まれた。開発、製造、営業の各部門からメンバーを募り少人数のチームを結成、開発に集中させた。従来のやり方は複数の開発案件が並行して緩やかに流れるスタイルだが、この時は猛スピードで開発を進め、わずか6カ月で製品を完成させた。これは従来の4倍のスピードだ。開発速度は上げても、「ものづくり」にはこだわっている。
(糖度計等製造・121人)
Step Up
(1)委員会やプロジェクトチームなど、部門横断的な組織を必要に応じてつくっている
部門間のなわばり意識を極力防ぐには部門を超えたメンバーを集めて、プロジェクトチームを構成し、部門横断的なテーマの解決を図るやり方があります。このような活動が活発な企業では原籍にかかわらずに、全社的な視点から議論ができる人材が育ってきます。
しかし、プロジェクト・マネージャーの選抜では検討課題分野の専門能力からマネージャーを決めるべきで、年功的な選抜にしてはいけません。また、中小企業の場合は全面的に任せるというよりも、社長自らがプロジェクトのテーマ設置、節目でのチェックに関わることが多いのですが、意識的にプロジェクト・マネージャーに権限委譲をすることが大事です。
(2)部門間の人事異動や人材交流を進めている
独創的な発想は、日常の仕事を繰り返しているだけではなかなか出てきません。3年とか5年とかを節目にして部門を超えた人事異動をすることで新たな発想が出てくるものです。その際に重要なのはどのような人材に育ってほしいのかを意識しておくことです。人材育成には専門性を極めるI型の育成形態と、10年ほどは専門性を積み上げ、その後に関連分野を広げていくT型の育成形態とがあります。研究所などは前者ですが、多くの日本企業のビジネスマンは後者のT型をめざしています。経験年数が10年ほどになったら、意識的に周辺の異分野の仕事に人事異動をするわけです。営業から人事とか、製造からサービスとかへの異動のイメージです。こうすることで、部門間のコミュニケーションは格段に改善されます。
 はじめての方
はじめての方 無料経営分析
無料経営分析 お問合せ
お問合せ ログイン
ログイン